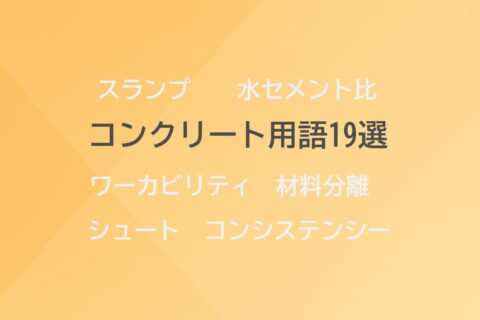この記事では、「2級土木施工管理技士」試験によく出るスランプや空気量の許容誤差、コンクリートの圧縮強度のJIS判定基準について詳しく解説します。
特に、「スランプや空気量の許容範囲ってどう覚えればいいの?」「JIS基準の数字ってどこまで必要?」と悩んでいる方に向けて、 過去問ベースでそのまま本番に出るポイントを整理しています。
スランプ・空気量・強度の違いや基準値をしっかり押さえて、試験対策に活かしましょう。
ちなみに「スランプ」とは、フレッシュコンクリート(生コン)のやわらかさ(施工しやすさ)を数値化したものです。値が大きいほど軟らかく、小さいほど硬いと考えればOKです。
📖 「土木施工管理技士の効率的な勉強法や経験記述」についてNoteで詳しく解説しています!
👉「土木施工管理技士の試験対策」Note記事を今すぐチェック!
※本記事はアフィリエイト広告を含みます。
目次
🔍この記事でわかること
- スランプと空気量、それぞれのJISにおける許容誤差の基準値
- スランプの範囲別に異なる誤差と、空気量の固定誤差の違い
- 圧縮強度の判定における平均値・最低値の見方と計算方法
- 実際の過去問を通じた、JIS基準の適用例と考え方
✅この記事を書いている人
| 所持資格 | 特記事項 |
|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | 一発合格 |
| 1級造園施工管理技士 | 一発合格 |
| 建設業経理士2級 | 一発合格 |
| 測量士補 etc | 一発合格 |
🦺 現役で建設業に従事、実体験に基づく勉強法を紹介!
① スランプとは?施工性との関係とJIS基準の基本問題
◆ スランプの性質と施工性に関する問題
【問題】
コンクリートのスランプに関する次の記述のうち、適切なものはどれか?
(1) スランプが小さいほど、作業性が向上する。
(2) スランプは、運搬、打込み、締固めなどの作業に適する範囲内でできるだけ小さくする。
(3) スランプは、コンクリートの強度を直接示す数値である。
(4) スランプが大きいほど、常に良質なコンクリートであると判断できる。
✅【正解】(2)
解説
- (1) 誤り:スランプが小さいほどコンクリート(生コン)は硬くなり、施工が難しくなるため、作業性はむしろ悪くなる。
- (2) 正しい:スランプは施工性(ワーカビリティー)確保のための指標。ただし、大きすぎると品質低下につながるため、「必要最小限」が基本。
- (3) 誤り:スランプは施工性(ワーカビリティー)の指標であり、強度の指標ではない。
- (4) 誤り:スランプが大きいと施工しやすくはなるが、材料分離が起きやすくなるため、「良質」とは限らない。
② スランプ試験の基礎知識とJIS測定ルール
【問題】
コンクリートのスランプ試験に関する次の記述のうち、適切なものはどれか?
(1) スランプ試験は、高さ50cmのスランプコーンを使用して測定する。
(2) スランプは、0.5cm単位で表示する。
(3) スランプ試験では、コンクリート中央部の平板からの高さを測定する。
(4) スランプは、コンクリートのブリーディング量を示す指標の一つである。
✅【正解】(2)
解説

- (1) 誤り:JISで定められたスランプコーンの高さは 30cm。50cmではない。
- (2) 正しい:スランプ値は 0.5cm単位で表示する。
- (3) 誤り:スランプ試験では、スランプコーンを引き上げたあとの、上端からの下がり幅を測定する。平板からの高さではない。
- (4) 誤り:スランプは施工性(ワーカビリティー)を表すものであり、ブリーディング量の指標ではない。
③ 練上り時の目標スランプの問題
問題
荷下ろし時の目標スランプが8cmであり、
練り上げから現場までの運搬中にスランプが2cm低下すると予測されている。
このとき、練り上げ時点での目標スランプとして適切なのは?
(1) 6cm
(2) 8cm
(3) 10cm
(4) 12cm
✅【正解】(3) 10cm
解説
スランプとは、コンクリートの軟らかさ・施工性(ワーカビリティ)を表す指標です。現場での施工がスムーズに行えるよう、適切なスランプ値を保つことが求められます。
- 荷下ろし時の目標スランプ:8cm
- 運搬中に予想されるスランプの低下:2cm
→ 8cm(目標)+2cm(低下分)= 10cm が適切
難しく考えず、単純に考えればOK!
✅ ワンポイント
「〇cm低下するから逆算して調整する」という問題は頻出!
④ 圧縮強度試験のJIS判定基準の過去問
問題
呼び強度21のレディーミクストコンクリートにおける、以下の圧縮強度試験結果をもとに、合格工区を選べ。
| 工区 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|
| A工区 | 19 | 20 | 21 | 20 |
| B工区 | 25 | 19 | 16 | 20 |
| C工区 | 20 | 22 | 21 | 21 |
| D工区 | 23 | 27 | 17 | 22 |
✅【正解】(3) C工区
解説
判定基準(JIS A 5308)
| 判定項目 | 基準値 | 内容 |
|---|---|---|
| 3回の平均値 | 呼び強度以上(21N/mm²) | 3回の平均 |
| 各1回の最小値 | 呼び強度の85%以上(17.85N/mm²) | 個別のばらつきが小さいこと |
→ 試験値は 18N/mm²以上 が必要
各工区の評価
| 工区 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|
| A工区 | 19 | 20 | 21 | 20✕ |
| B工区 | 25 | 19 | 16✕ | 20✕ |
| C工区 | 20〇 | 22〇 | 21〇 | 21〇 |
| D工区 | 23 | 27 | 17✕ | 22 |
※平均値は「3回の試験値の合計 ÷ 3」で求めます。 たとえば【19, 20, 21】の場合 →(19+20+21)÷3=20.0
- A工区:平均20 → ✕
- B工区:1回16N/mm² → ✕
- C工区:平均21、全て18以上 → 合格
- D工区:1回17N/mm² → ✕
⑤ 空気量・スランプ・圧縮強度の総合問題
問題
呼び強度21、スランプ12cm、空気量4.5%の指定に対して、以下の試験結果が得られた。
JIS基準に不適合なものはどれか?
(1) 圧縮強度平均:23N/mm²
(2) 圧縮強度1回の値:18N/mm²
(3) スランプ:14.0cm
(4) 空気量:7.0%
✅【正解】(4) 空気量7.0%
解説
圧縮強度の判定
- 呼び強度:21N/mm²
- 平均値:21N/mm²以上 → OK
- 1回の値:21×0.85=17.85N/mm²以上 → 18N/mm²でOK
スランプの許容範囲
スランプの許容誤差は、指定されたスランプ値によって異なります(JIS A 5308より)。以下にまとめます:
| 指定スランプの範囲 | 許容誤差 |
|---|---|
| 5cm以上 8cm未満 | ±1.5cm |
| 8cm以上 18cm未満 | ±2.5cm |
→ 今回は12cm → 該当するのは「8cm以上18cm未満」 → 許容範囲は 9.5〜14.5cm → 14.0cmはOK
空気量の許容範囲
- 指定空気量:4.5%
- 許容誤差:常に±1.5%(固定)
→ 許容範囲は 3.0〜6.0%
→ 7.0%は 上限超過 → 不合格
※空気量はスランプと異なり、誤差幅が一定です。
✅ 空気量の誤差は±1.5%で固定と覚えておいてください。
◆ 最終まとめ表
| 判定項目 | 基準 | 判定 |
|---|---|---|
| 圧縮強度平均 | 21N/mm²以上 | 合格 (23N) |
| 圧縮強度1回値 | 18N/mm²以上(85%) | 合格 (18N) |
| スランプ | 9.5~14.5cm | 合格 (14cm) |
| 空気量 | 3.0~6.0% | 不合格 (7%) |
⑥ JIS基準|スランプ・空気量・圧縮強度の覚え方
● 「以上」「未満」などの用語に注意!
たとえば「8cm以上18cm未満」とあった場合:
- ⭕ 8.0cm → 含まれる(OK)
- ❌ 18.0cm → 含まれない(NG)
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| ○○以上 | ○○を含む |
| ○○以下 | ○○を含む |
| ○○未満 | ○○を含まない |
| ○○を超える | ○○を含まない |
✅ ポイント:「以上」「以下」はその値を含む、「未満」「超える」は含まない! → 試験ではスランプ値などでこの違いが重要な判断基準になります。
📖 「土木施工管理技士の効率的な勉強法や経験記述」についてNoteで詳しく解説しています!
👉「土木施工管理技士の試験対策」Note記事を今すぐチェック!
最後に、試験対策として重要な数値と違いをまとめます:
● 重要:スランプの許容誤差
| 指定スランプの範囲 | 許容誤差 |
|---|---|
| 5cm以上 8cm未満 | ±1.5cm |
| 8cm以上 18cm未満 | ±2.5cm |
→ 値に応じて変わる。スランプは「可変」誤差。
8cmを境に許容誤差が変わります。
未満と以上に注意!
📖 「土木施工管理技士の効率的な勉強法や経験記述」についてNoteで詳しく解説しています!
👉「土木施工管理技士の試験対策」Note記事を今すぐチェック!
● 重要:空気量の許容誤差
- 常に ±1.5%(固定)
→ 値によらず一律の基準。空気量の許容誤差は「固定」。
● 重要:呼び強度・圧縮強度試験の基準
- 平均:呼び強度以上
- 1 回:呼び強度の85%以上(例:21×0.85=17.85 → 18N/mm²未満はNG)
● 独学は不安という人は

難しい資格試験で、絶対に合格したいけど...
どうやって勉強すればいいのか分からない....。という方も多いと思います。
そんな時は通信講座を受講してしまうのも選択肢の一つです。
通信講座は、合格まで一直線のカリキュラムなので、
勉強方法に迷うことがありません。
例えば、アガルートアカデミーの土木施工管理技士講座(SAT提供)は、全て収録されたオンライン映像にて受講するため、通学型の予備校よりも安く受講することができます。
◆土木施工管理技士講座(SAT提供)が選ばれる理由◆
- マルチデバイス(パソコン/スマートフォン/タブレット)対応。
- 1つの動画につき10~20分程度なので、無理なく続けられます。
- スマホを使って、ちょっとしたスキマ時間に勉強ができます。
- TVを見る感覚で学習ができるのでとても楽です。
- 動画での学習が身についているか、確認問題で実力試しができる。
- オリジナルテキストは、フルカラーで分かりやすいレイアウトなどの工夫が随所に見られます。
- 倍速再生(8段階速度調整,かつ最大3倍速)でさらに時短学習。
- 講師自ら出題傾向を分析し合格に必要な情報が詰めこまれています。
アガルートの土木施工管理技士講座(SAT提供)の詳細はこちら
✅ おわりに
スランプ、空気量、圧縮強度のJIS判定基準は、毎年多くの受験者がつまずくポイントです。
でも、覚えるべき数値や考え方は、こうして整理すれば決して難しくありません。
「何から覚えればいいか分からない」
「なんとなく理解した気になっていたけど、ちゃんと説明できない」
そんな人こそ、この記事で紹介した内容を実際の過去問にあてはめて確認してみてください。
きっと、“なんとなく”が“わかった”に変わるはずです。
少しずつでいいので、自分のペースで取り組んでいきましょう。
あなたの合格を、心から応援しています!
📖 「土木施工管理技士の効率的な勉強法や経験記述」についてNoteで詳しく解説しています!
👉「土木施工管理技士の試験対策」Note記事を今すぐチェック!
あなたのおすすめの記事!
-

【土木施工管理技士】コンクリート工事の用語や意味をやさしく解説!試験対策にどうぞ!
2025/10/12
ワーカビリティー、スランプ、コンシステンシーなど、コンクリートに関する基本用語は、1級・2級土木施工管理技士試験で頻出です。この記事では、施工・配合・材料に関する用語をカテゴリごとにわかりやすく解説し ...
-

【よく出る】コンクリートの打ち重ね時の施工ポイントと過去問解説!【1級土木施工管理技士 第二次検定】2級受験者も必見!
2025/10/12
🔹 はじめに コンクリート構造物の施工では、打ち重ね時の管理が非常に重要です。上層と下層を一体化させるための施工技術を理解していないと、接合不良が発生し、強度不足につながる可能性があります。 1級土木 ...
-

【よく出る】マスコンクリートのひび割れ対策を過去問解説!【1級土木施工管理技士 第二次検定】2級受験者も必見!
2025/10/12
🔹 はじめに コンクリート施工において、「ひび割れ」は耐久性や構造強度に大きく影響する重大な問題です。特にマスコンクリートでは、沈みひび割れや温度ひび割れが発生しやすく、1級土木施工管理技士試験の第二 ...
-

コンクリートの締固め・打ち継ぎ・コールドジョイントを徹底解説!【1級・2級土木施工管理技士】試験対策ポイントまとめ🏗️
2025/10/12
「コンクリートの締固めや打ち継ぎって、試験でよく出るけど分かりにくい…」 そんなあなたへ!✨ 1級・2級土木施工管理技士の試験では、コンクリートの締固め・打ち継ぎ・コールドジョイントに関する問題が頻出 ...
-

【令和7年度】経験記述の書き方【2級土木施工管理技士・第二次検定】
2025/10/12
土木施工管理技士の第二次検定において、「経験記述」は合否を左右する重要な部分です。しかし、多くの受験者が… ✅ 「何を書けばいいのか分からない…」✅ 「経験が少なくて不安…」✅ 「市販の参考書の例文を ...